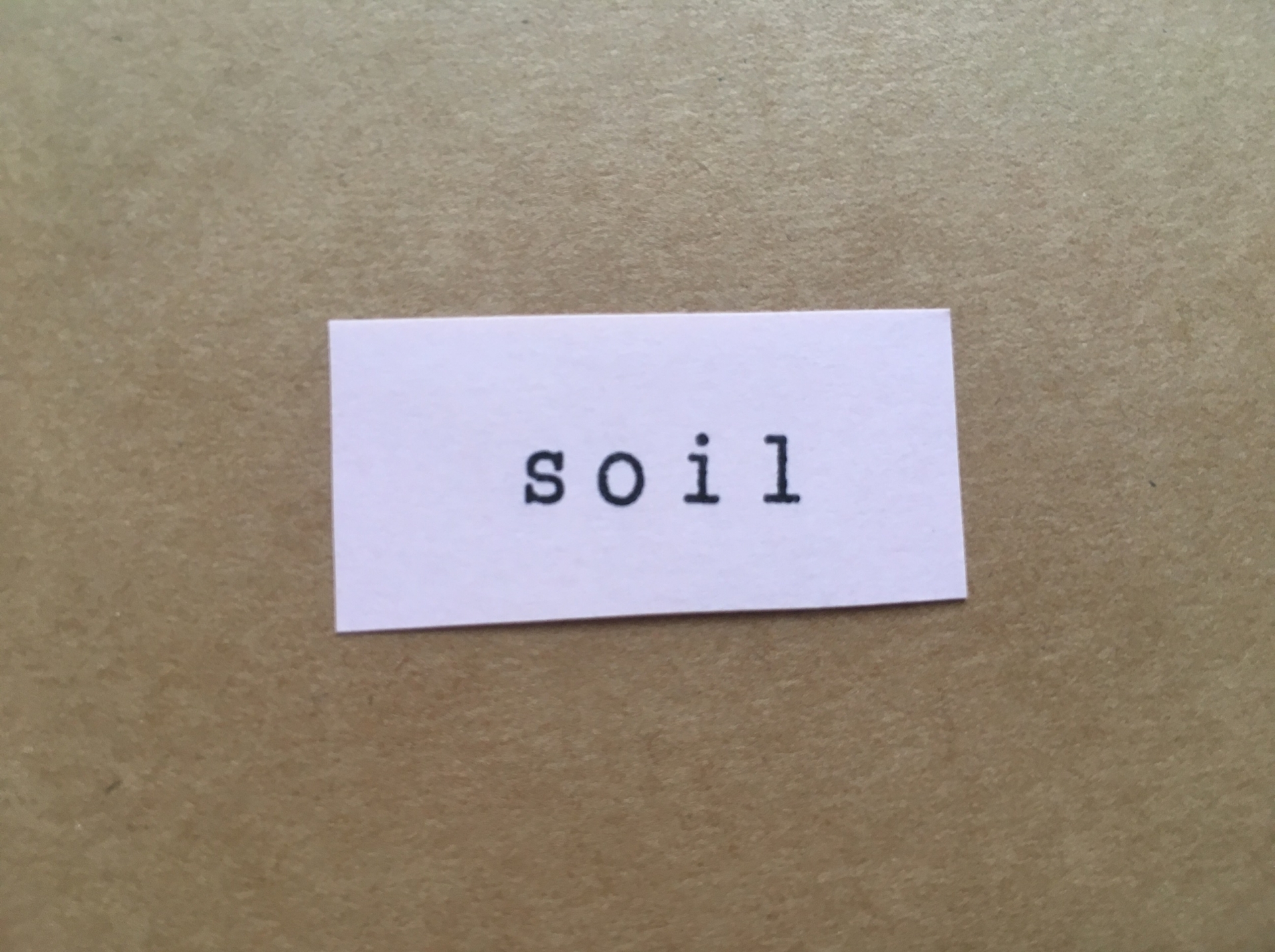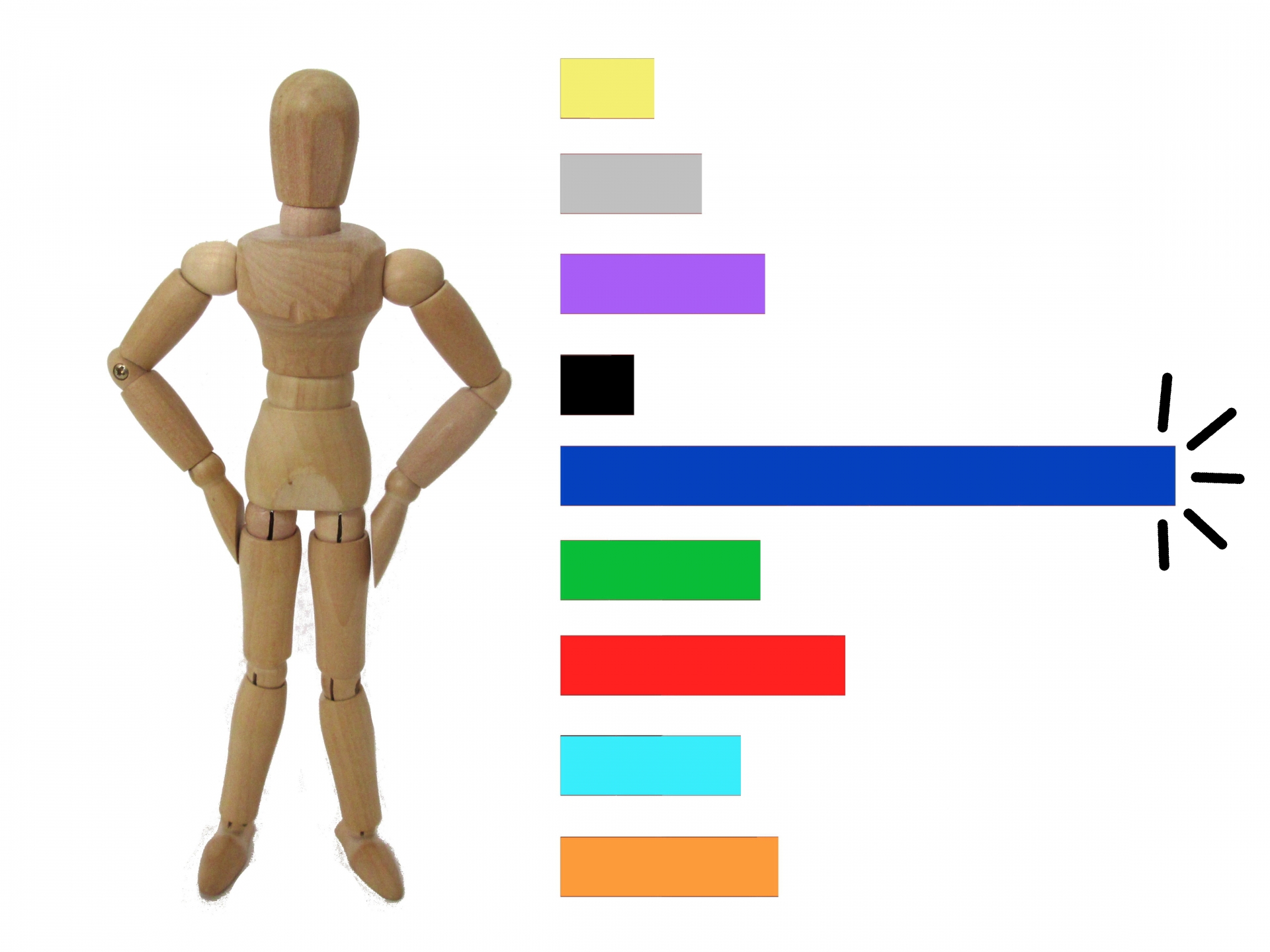樹脂粘土を使ってフィギュアを作ることができると聞いても、初心者は何から始めればいいのかわからないでしょう。
今回は、初心者向けに樹脂粘土を使ったフィギュアの作り方とコツについて説明します。まずは、自分が作りたいものをイメージすることから始めましょう。ただし、最初は簡単なものを選んだ方がよいでしょう。
また、着色方法についても説明します。何回も繰り返して作るうちに、だんだんクオリティも上がっていくでしょう。それまでは数をこなすようにしましょう。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
スポンサーリンク
樹脂粘土を使った簡単なフィギュアの作り方
失敗しないフィギュアの作り方は、初心者はシンプルな形から。
まずはじめにフィギュアのイメージを描く事が必要
初心者の場合は、あまり凝ったデザインにせず単純な形を意識してデザインを考えましょう。
デザインを考えたら骨組みとなる芯を作っていきます。針金にテープを巻き付けてから針金を曲げてポーズなどを整えます。この時、全体のバランスも確認して作業しましょう。
樹脂粘土で肉付けして形を整える
芯ができたら樹脂粘土を盛り付けて肉付けしましょう。水の量を加減しながら表面がデコボコにならないようにすると、色付け作業もスムーズになります。
フィギュアの着色、仕上げ
全体の形が整ったらアクリル絵の具などを使って着色していきます。細かい部分まで丁寧に塗り分けるとワンランク上の出来上がりになります。
樹脂粘土を使った人間型フィギュアの作り方のコツ
樹脂粘土の扱いにも慣れてきたら、より精巧な人間型のフィギュアにも挑戦してみましょう。
フィギュアの繊細な形の作り方
異なる太さの針金を組み合わせて芯を作る
手足が細いリアルな人間の形状では芯の作り方が大切になります。針金にテープを巻いただけでは樹脂粘土の定着が悪く肉付けがしにくくなります。
そこで、より細い針金を巻き付けて樹脂粘土の食いつきを良くしましょう。
より細かい造形には焼成ができる樹脂粘土がお勧め
顔の部分やボディに細かいパーツがある場合には、オーブンで焼くことで硬化する焼成可能な樹脂粘土がお勧めです。
一般的な樹脂粘土は乾燥とともに収縮して変形することがありますが、焼き固めることで変形を防ぎ、耐久性も上がるので細かな造形に適しています。
また、細かいパーツを作る自信がない場合にはプラモデルなどの既存パーツを利用してもいいでしょう。
樹脂粘土のフィギュアの作り方で大切な色の着け方について
樹脂粘土を使ってフィギュアの形状が完成したら、イメージ通りに着色していきましょう。
フィギュア完成後に着色する
入手しやすく作業しやすいものとしてはアクリル絵の具があります。質感のイメージによってはプラモデルようのエナメル塗料やラッカーを使っても表現の幅が広がります。
メタルカラーやグロスを表現したい場合は、プラモデル用塗料の方が向いているでしょう。筆を使って塗る方法意外にも、エアブラシを使うとムラができず均一な色付けができます。
あらかじめ樹脂粘土に混ぜ込んで着色する
樹脂粘土はアクリル絵の具を混ぜ込んで直接色を付ける作り方もあります。肌の色の柔らかい表現や、構造が複雑で後からの着色が難しい場合には樹脂粘土に色をつけて細かい部分だけ筆を使って着色することもできます。
完成後にニスで質感アップ
着色が終わったフィギュアは、ニスを塗って仕上げます。
100均の樹脂粘土でフィギュアを作ってみましょう
樹脂粘土は画材・文具店やホビー売り場などで取り扱われていますが、手始めに試してみたいのであれば100均でも購入が可能です。
量が少なめなので大きな作品を作るよりも、小さなものを作ったり初心者が試してみるにはピッタリです。一般的な樹脂粘土と作り方は全く同じで、成形して自然乾燥でOK。徐々に品揃えも増えており、焼成できるオーブン粘土も選べます。
樹脂粘土は初めから色がついているので簡単
100均の樹脂粘土には、白だけでなくピンクやブルー、ブラックやブラウンといったあらかじめ着色されたものがあり、着色の手間も省けます。
異なる色の樹脂粘土を混ぜて新たな色の樹脂粘土を作ることも可能です。
樹脂粘土は乾燥させることで硬化する
しっかりと乾かすことがとても重要
厚みのある形の場合は3~4日間ほどかかる場合もあるので、早く仕上げたい場合には厚みや大きさに注意しましょう。
急いで乾燥させると変形やひび割れの恐れがあります。また、ドライヤーの高温で発火する危険性もあるので要注意です。
樹脂粘土以外の粘土でもフィギュアを作ることができます
今回はフィギュアの作り方として樹脂粘土を使って説明してきましたが、これ以外にもフィギュア作りに使用できる粘土はあります。
紙粘土
言わずと知れた紙粘土。子供の頃から何度もお世話になったことと思います。この紙粘土でもフィギュア作りは可能です。
入手もしやすいので気軽に始められるメリットがあります。
石粉粘土
プロの造形作家も使う石粉粘土は、細やかな造形も可能で人形作家にも愛用者が多い粘土です。
粒子が細かく、仕上がりがなめらかになります。完成後に削って整えることもできるメリットがあります。
粘土にはそれぞれ性質に違いがあるので、作りたい作品に合わせて選ぶことが大切
今回は主に樹脂粘土を使ったフィギュアの作り方を解説しましたが、気軽に楽しむのであれば誰もが使ったことのある紙粘土でも作品を作る楽しみを感じることができると思います。