飼育しているカナヘビが卵を産み、その卵にカビが生えてしまったら、一体なぜそのような状況になるのか知識がないと分からないものです。カビが生えた卵でも、そのまま飼育しても問題はないのでしょうか。
ここでは、カナヘビの卵にカビが生えた原因と対処法についてお伝えします。卵のカビの原因を知って、上手に飼育してあげましょう。
また、カナヘビの卵を孵化させるまでの手順やポイントについてもお伝えします。こちらも参考にして、元気なベビーを誕生させてあげましょう。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

コリドラスの水槽に水草は入れない?おすすめの水草と入れ方解説
コリドラスを飼育するときは、水槽の中に水草を入れずに飼育することが多いです。まだコリドラスの...
-

スッポンの飼育で餌の与え方と気をつけたい注意点や飼い方のコツ
スッポンの飼育では、餌の与え方が大切になります。スッポンを飼育する初心者だと、どんな餌を与え...
-
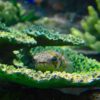
ミドリフグを飼育する時のポイント・初心者でも簡単に飼育できる
これからミドリフグを飼育してみたいと考えている人もいますよね。ミドリフグは、熱帯魚初心者でも簡単に飼...
-

カナヘビの卵がへこんでいるのは無精卵の可能性が!卵の見分け方
カナヘビの卵を育てている時、他の卵と様子が違う卵があった場合は無精卵の可能性があります。なかなか卵が...
スポンサーリンク
カナヘビの卵にカビが生えた原因
カビの生える原因や、カビの生えた卵への対処法を知らないと、他の卵にまで影響を及ぼしてしまうので、カビが生える原因などについて知っていきましょう。
カナヘビの卵にカビが生える原因は、その卵が無精卵だからです。
無精卵があることは、カナヘビに限ったことではありません。
産卵する生き物であれば、どの生き物にも有精卵と無精卵があります。
この有精卵と無精卵の決定的な違いは、孵化する準備が行われているかいないかです。
有精卵の中には当然胎児がいるので、卵の中で生まれるための成長を始めます。
胎児は必要な空気や水分を吸収して孵化する日を待ちます。
卵の中の胎児が空気や水分を吸収することによって、有精卵の表面にカビが生えるということは絶対に起こりません。
しかし中に胎児がいない無精卵の場合、もちろん空気や水分は吸収されることはありません。
高温多湿なカナヘビのケージの中で、どんどん湿度が増していくので卵にカビが生えてしまうのです。
カビが生えたカナヘビの卵を取り除く理由
では、なぜすぐにカビの生えた卵を取り除くのか、という理由について紹介していきます。
カビの生えたカナヘビの無精卵は、同じケージ内の有精卵、そして有精卵の中にいる胎児まで影響を与えてしまいます。
有精卵にカビの菌が移ってしまうと、卵の表面に菌糸を張り巡らせて繁殖を始めます。
菌糸に卵の表面を覆われてしまうと、空気や水分が吸収出来なくなり、胎児の生命維持の邪魔をしてしまいます。
これでは孵化するまでに必要な成長を遂げられず、卵の中で命を落としてしまう危険性があります。
命を落とさないとしても、カビから放出される毒素によって、抵抗力の弱い胎児に何らかの異常を与える場合もあります。
異常を持って生まれた胎児は、その後健康的に成長出来るかわかりません。
孵化を待つ有精卵にまで影響が及ばないように、個数には関係なくカビの生えた卵は全て取り除く必要があります。
へこんだままのカナヘビの卵のカビ
産卵されたカナヘビの卵は柔らかいという特徴があります。
有精卵と無精卵で比較すると、無精卵の方がより柔らかいのですが、カナヘビの卵に対しての知識や経験の少ない方は、その判断をすることも難しいでしょう。
産卵から間もない卵はどちらも柔らかく、へこみが見られることもありますが、有精卵と無精卵ではそのへこみの状態にも変化が生じます。
卵の中で胎児が成長していく有精卵は、時間の経過とともに吸収された空気や水分の影響でへこみがなくなっていきます。
そして、卵そのものの大きさにも変化が表れます。
一方無精卵の場合は、時間が経過して表れる変化はカビが生えることで、卵のへこみはそのままです。
時間が経過しても卵がへこんだままであれば、無精卵である可能性が高く、さらにカビが生えてくるようなら間違いなく無精卵と判断出来ます。
無精卵ではなくても、卵が本来の上下の位置と逆さまになってしまうと、残念ながら胎児は成長することが出来なくなり、へこみがそのままになっている場合もあります。
この場合もカビが発生するようになり、卵の見た目は無精卵と同じ状態です。
カビが生えていないカナヘビの卵の飼育環境
カビが生えていないカナヘビの卵は、おそらく胎児が孵化に向けて成長しています。
無事に孵化出来るように適切な環境で卵を飼育してあげましょう。
母カナヘビが産卵したら、卵を回収して別の容器に静かに移してあげるとより安全です。
また、母カナヘビのエサとして一緒にケージ内にコオロギがいる場合、柔らかな卵は食べられてしまう危険性があります。
どちらの場合でも、胎児が孵化することはありません。
このような事態を防ぐためにも、卵の上下が一目でわかるように目印を付けてから、卵だけでの飼育を始めます。
卵は湿った土の上で飼育することになります。
土の水分が乾かないように定期的に水分を補給して、容器の内側にも水分を与えましょう。
容器には蓋をして乾燥を防ぎます。
しかし、直接卵を水で濡らすようなことはしないで下さい。
カナヘビの卵が孵化するまでにかかる期間
カナヘビの卵の飼育環境や、カビが発生してしまう原因などを紹介してきました。
ここでは無事に孵化を迎えるカナヘビの卵についての説明をしていきます。
カナヘビの卵は、産卵から約一ヶ月すると孵化して赤ちゃんが生まれます。
この頃になると、産卵したときの状態に比べると、卵の大きさの2倍ほどに大きくなっています。
孵化の瞬間を迎えると、卵にヒビが入って中の水分が一気に外へと溢れ出します。
水分が出たせいで、卵は半分程度の大きさにまでなります。
あとはゆっくりと時間をかけながら、慎重に赤ちゃんは孵化を始めます。
ですが飼い主である人間に出来ることはありません。
とにかく優しく見守ってあげることです。























