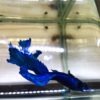カナヘビの卵を育てている時、他の卵と様子が違う卵があった場合は無精卵の可能性があります。なかなか卵が大きくならず、状態が改善しないようであれば、無精卵を疑ってみましょう。
ここでは、カナヘビの卵が無精卵だった場合の特徴や見分け方についてお伝えします。カナヘビの卵の状態を確認して、無精卵かどうかを見分けましょう。
カナヘビの卵が無精卵だった場合は、それに合わせた対処をする必要があります。飼い主さんがしっかりと管理をしてカナヘビの卵を孵化させてあげましょう。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

カブトムシの幼虫が出てくる原因が土の中のガスだった時の対処法
カブトムシの幼虫を育てていて、ふと見ると幼虫が土から出ていることがあります。土から出てくる原...
-

ミナミヌマエビの水槽に入れる水草に付着した残留農薬の除去方法
ミナミヌマエビを飼育している人の中には、水槽の中に水草を入れたいと考えている人もいるのではないでしょ...
-

ウサギのケージの掃除の仕方と道具を紹介。頻度や選ぶポイントも
見ているだけで癒されるウサギはペットとしても人気です。ウサギは自然界では穴で暮らす生き物なので、...
-

文鳥が餌を食べにくそうにしている?餌入れの底上げをしてみよう
文鳥のケージについてきた餌入れを使用していると、深さがあるため文鳥が食べにくそうに感じる場合がありま...
スポンサーリンク
カナヘビの卵が孵化しないのは無精卵だからかも
カナヘビは飼育環境が整っていると、たくさんの卵を産みます。
6月~7月の暖かい季節に産卵するカナヘビは、一度に1個~8個くらいの卵を産みます。
しかし、産まれた卵が全て孵化するというわけではなく、中にはなかなか孵化しない卵もあります。
カナヘビの卵には、産卵直後にへこみがあるものがあります。
湿った土がある良い環境の場合は、通常水分を含んで徐々にへこみは解消されていきます。
それでも卵が膨らまずにへこんだままなら、その卵は無精卵である可能性が高いです。
無精卵は孵化することはないので、すぐに他の卵から離すため取り除く必要があります。
無精卵のカナヘビの卵は柔らかい
ですが無精卵はそれ以上に柔らかく、カナヘビの卵を今まで見たことがある方なら違いに気付くと思います。
しかし、カナヘビの飼育や産卵について初心者の方だと、有精卵と無精卵の柔らかさの違いがわからない場合もあります。
柔らかさで有精卵と無精卵の判断が難しい場合は、カナヘビの卵のへこみを参考にしてみて下さい。
カナヘビの卵は、通常約一ヶ月程度で孵化します。
産卵から一週間くらい卵の様子に変化がなく、へこみがそのままの状態であれば、無精卵である可能性が高いです。
ケージから取り除く準備をしなければなりません。
産卵したばかりの卵のほとんどはへこみがあるものが多く、卵の中の胎児の成長とともに目立たなくなります。
なので、産卵後すぐに無精卵という判断はせず、一週間くらい様子を見た上で判断するようにして下さい。
カナヘビの卵にカビが生えたら無精卵の可能性が高い理由
それは、無精卵にはカビが発生してしまうからです。
有精卵の中には胎児がいて、日々生まれるための成長をしています。
無精卵の場合は当然胎児がいないので、卵の中では何の変化や成長もありません。
有精卵の場合は胎児が空気や水分を吸収しているのですが、無精卵の場合は空気や水分の吸収もありません。
そのため、高温多湿というカナヘビを飼育しているケージ内の環境では、卵にカビが発生してしまうのです。
卵の表面にカビが繁殖してしまうと、胎児は必要な空気や水分を吸収することが出来なくなり、命に関わる事態にもなりかねません。
カビは少なからず毒素を排出しているので、胎児にとっては負担が大きすぎます。
他の卵を守るためにも、すぐに取り除いて下さい。
カナヘビが卵を産んだらすぐに回収を
カナヘビが産卵したら、すぐに卵を回収出来るといいのですが、そのためには産卵の兆候についても知っておく必要があります。
産卵が近付いてくると、メスのお腹は卵を蓄え大きくなります。
そして動きが少なくなってきます。
いよいよ産卵の前日になると、産卵出来る場所を探すために今まで動くことが少なかった母カナヘビの動きが活発になってきます。
静かだったカナヘビが突然活発になったら、もうすぐ産卵という兆候です。
産卵そのものは1分程度のごく短時間で終わります。
早ければ数秒で産卵を終える、というカナヘビもいるので見逃してしまいそうですね。
母カナヘビが産卵を終えたら、卵を回収して保護します。
カナヘビの卵は、成長の途中で上下が逆さまになってしまうと、中にいる胎児は窒息して命を落としてしまいます。
また、親カナヘビのためにエサとしてコオロギを一緒に入れている場合は、このコオロギが卵を食べてしまうこともあるのです。
カナヘビの卵は有精卵でも柔らかいので、直接手で掴んだりせずにスプーンなどを使って静かに保護して下さい。
カナヘビの卵のお世話方法
産卵を終えた母カナヘビは、その後何もしないので飼い主が卵のお世話をすることになります。
無精卵を取り除くことはもちろん、有精卵が無事に孵化出来るようにお世話もします。
卵の上下が必ず分かるようにする
せっかく卵を保護しても、途中で卵の上下が分からなくなっては大変です。
常に卵の上下がはっきり分かるように、必ず目印を付けて逆さまになってしまうことのないようにします。
ケージの環境
保護した卵は、プラスチックの容器などに入れます。
必ず土を敷き、くぼみを作った上に静かに卵を置いてあげて下さい。
卵の中の胎児が水分を吸収出来るよう、土には十分に水分を与えて湿らせて下さい。
卵は思っている以上にデリケートなので、直接刺激を与えないで下さい。
一週間に一度は土の水分を補充して、乾燥しないように容器には蓋をしましょう。
中には孵化の途中で力尽きてしまうカナヘビの赤ちゃんもいますが、飼い主が手伝ってあげることは出来ません。
温かく見守ってあげましょう。