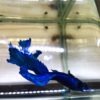大切に飼育している金魚にウオジラミが寄生しているかもしれないとわかった場合、どのように治療したらいいのか悩むこともあるでしょう。
また、いつの間についてしまったのだろうと原因がわからずに不安になる人も多いのではないでしょうか。
しかし、原因を理解し正しい治療をすることによって金魚を長生きさせることも可能です。
今回は金魚にウオジラミが寄生する原因とその駆除、治療方法について説明します。寄生しているとわかった時点ですぐに取ってあげましょう。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

メダカのアクアリウムの道具が100均にある。おすすめアイテム
水の中を自由に泳ぐメダカは見ていて飽きないですね。アクアリウムが人気を集めていますが、始める...
-

セキセイインコのおもちゃの作り方。材料や手順や人気のおもちゃ
セキセイインコが今のおもちゃに飽きた様子はみられませんか?そんな時はおもちゃを手作りをしてみまし...
-

スッポンの飼育で餌の与え方と気をつけたい注意点や飼い方のコツ
スッポンの飼育では、餌の与え方が大切になります。スッポンを飼育する初心者だと、どんな餌を与え...
-

水槽に白い虫発生!小さいものなら害なし?その正体を明かします
熱帯魚などを飼っていると、水槽に小さい白い虫がついていることがありますよね。その気持ち悪さに...
-

【アカヒレの飼育】屋外の場合の注意点とコツについて説明します
初心者でも飼いやすいと言われるアカヒレですが、屋外だけではなく場所によっては屋外での飼育も可能となっ...
-

コリドラスの水槽に水草は入れない?おすすめの水草と入れ方解説
コリドラスを飼育するときは、水槽の中に水草を入れずに飼育することが多いです。まだコリドラスの...
スポンサーリンク
金魚にウオジラミが寄生する原因と治療方法について
飼育中の金魚にウオジラミが発生してしまったら、まずは新しく購入してきたりした水槽内の新入りである生体の体をよく調べてみましょう。
ウオジラミが発生してしまう原因は、基本的には新規導入したお魚からの感染がほとんどです。
外部から持ち込まれるウオジラミは専用の駆除剤などでの対処が必要となってきます。
発見時直ぐにできることだと、ピンセットで金魚の体表に見えるウオジラミを取り除いてあげることです。
ですがこうした対処ではすべてを取り切るのは難しい上に、もし金魚の体表に卵が産み付けられている状態ではそれを取り除くまでに至ることが出来ません。
金魚の体表にいたウオジラミを金魚を傷つけないようきれいに取り払ったら、しばらくの間は注意深く様子を見守ったほうがいいでしょう。
ウオジラミは成虫は目に見える程度の大きさをしていますが、卵までは人間の目では発見し切ることは難しいです。
一度発生してしまうと撲滅するまで安心できませんので、しっかりとした対処を早急に行いましょう。
金魚のウオジラミは動物病院で治療することはできません
金魚のウオジラミは動物病院での治療は行えない症状となります。
もしご自宅の金魚に発生してしまった場合は根気よくピンセットでの対処と薬浴を続けていくほかありません。
ウオジラミの治療はひとつの水槽内に金魚が数匹いて発生した場合はすべての金魚の様子を注意しなくてはなりません。
ウオジラミは感染していきますので、成虫のウオジラミがいた金魚は隔離して治療を行うほかに、同じ水槽で暮らしていた他の金魚たちにも感染がないかを確認しつつ過ごさなくてはなりません。
ですがウオジラミが発生してしまったからといって、対処を行えば金魚たちはまた元気に暮らすことが出来るようになります。
そうするために発見した際には急速な対応が必要となります。
治療となる行動は
- ピンセットでの対処
- 水質改善
- 隔離
- 薬浴
この4つです。
くれぐれも虫を駆除しようとヒーターなどで水温を上げすぎたりという行動で金魚に負担をかけないようにしましょう。
ウオジラミが寄生した金魚を治療しないと命を落とす可能性も
ウオジラミは虫です。
そのため、金魚の体表に住み着き金魚の血液を吸ったり毒素を注入したりすることで生きています。
そうした状態が長く続けば金魚は徐々に弱っていき最悪の場合、命を落とす結果となってしまいます。
ウオジラミに寄生されてしまった金魚は特徴として下記のような行動に出ている場合が多々あります。
- 水槽内に体をこすりつけている
- 他の金魚から離れてじっとしている
- 水面のあたりを元気なく漂っている
こうした特徴が金魚に見られたらウオジラミに寄生されている可能性があります。
体表をじっくりと観察しそういった状態にないかを確認してください。
ウオジラミは15~30℃ほどの水温を好む虫です。
そのため初夏から秋の半ばにかけて(6~9月頃)は水槽内の水質管理をしっかりと行うことが予防に繋がります。
ウオジラミがついた金魚をより早く治療する方法とは
ウオジラミがついた金魚を発見したらまずは隔離を行い成虫を駆除します。
そして金魚が元いた水槽もしっかりと環境をもとに戻す必要があるため、他に金魚を飼育していた場合はその金魚たちも寄生されていた金魚とは別の容器に引っ越しさせてそれぞれ薬浴を行わせるのがいいでしょう。
その間、水槽は金魚たちがいなくなった状態になるはずですので、きちんと洗浄し天日干しを行って完全に乾かします。
砂利などを敷いて飼育していた場合は砂利も煮沸を行い、水槽内の環境をリセットします。
水草などはウオジラミが残ってしまっている場合なども考えられるため、出来ることなら廃棄してしまうのが無難です。
ウオジラミ発生の際はすぐに治療に取り掛かるのが肝心です。
一匹でも見つけたらすぐに取り除き、水質改善を行いましょう。
金魚の薬浴の具体的な方法について
金魚の薬浴はリスクも有るため薬浴を行うときは、使用する薬の効能だけでなく副作用や強さなども把握した上で行いましょう。
ウオジラミ撲滅の際の薬浴は、カルキを抜いた新しい水を水温25℃ほどで使用します。
お水は0.5%ほどの濃度で塩浴させるお水にしたら、薬を入れていきます。
薬は完全撲滅のために3回ほど使いましょう。
2週間に一回、水換えと一緒に薬を投入する形で6週間ほど続けて使用します。
ウオジラミ用の薬は成虫になっているウオジラミに効くもので、卵の状態のものには効かないものであるため6週間ほどしっかりと薬浴させる必要があります。
卵が残っている恐れがなくなるのがだいたいその位の期間であるため、それを脱したら薬なしの状態で様子を見ましょう。
ウオジラミは早期治療が肝心です。
発見次第、即刻手を打ちましょう。