外でメダカを飼育していると、冬の寒さをどんなふうに乗り越えたら良いか悩んでしまうこともあります。そんなときは、発泡スチロールを活用してみましょう。
でも、実際にどのように使用すればいいのかわからなかったり、どうして発泡スチロールが向いているのか分からないと、上手に活用することができませんよね。
ここでは、発泡スチロールを使ってメダカを越冬させる方法についてご紹介します。発泡スチロールをうまく利用して、メダカを越冬させましょう。
また、発泡スチロール以外の越冬方法や水の量・餌の与え方についてもご紹介しますので、そちらも併せて御覧ください。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-
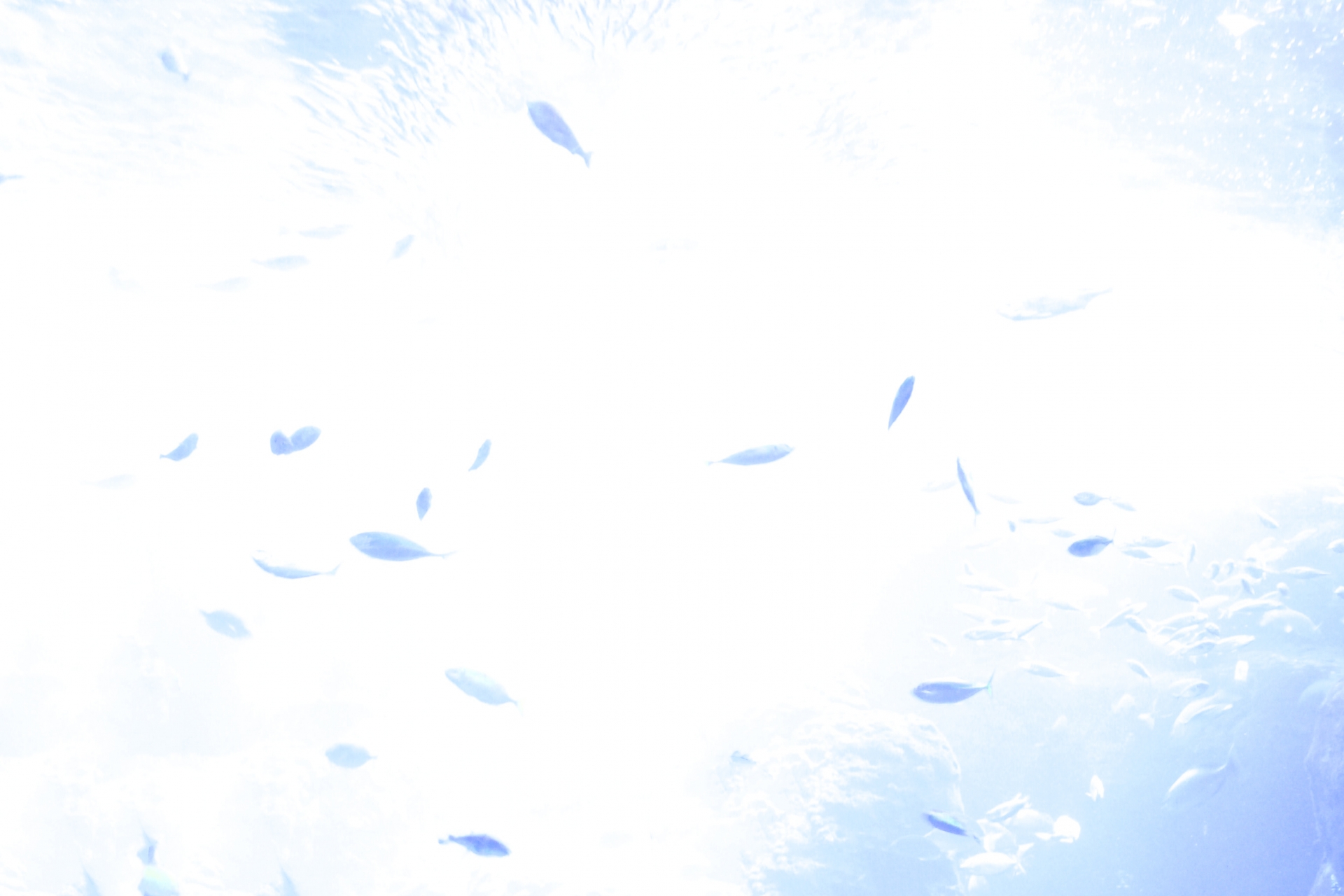
グッピーは出産後もお腹に精子を溜める!グッピーの出産について
グッピーの繁殖に挑戦しているという人もいるのではないでしょうか。まだ繁殖挑戦し始めたばかりだと、出産...
-

グッピーのメスの妊娠はお腹でわかる?見た目でわかる妊娠の兆候
グッピーのメスが妊娠していると、見た目でわかるくらいお腹に変化が見られます。特に出産間近のメスは...
-

ハムスターの交配は組み合わせが重要!異種交配は絶対に避けよう
ハムスターの交配では組み合わせによって奇形が生まれてしまったり、病気を引き起こしてしまう事があります...
-

ミナミヌマエビの水槽に入れる水草に付着した残留農薬の除去方法
ミナミヌマエビを飼育している人の中には、水槽の中に水草を入れたいと考えている人もいるのではないでしょ...
-

オカヤドカリの脱皮の頻度と飼い主のNG行動について説明します
オカヤドカリの動く姿を見ていると、なんともかわいらしいですよね。そんなオカヤドカリは脱皮をし...
-

カナヘビの卵がへこんでいるのは無精卵の可能性が!卵の見分け方
カナヘビの卵を育てている時、他の卵と様子が違う卵があった場合は無精卵の可能性があります。なかなか卵が...
スポンサーリンク
メダカを越冬させるときは発泡スチロールがおすすめ
メダカを越冬させるときは発泡スチロールが活躍します。
メダカは冬、水面に多少氷が張っていても生きていられる強い生き物です。
でも水槽の水全体が凍ってしまっては息ができません。
そんな状態にさせないためにあまり凍らない容器、凍ってもすぐに解かせる容器が必要になります。
冬に最適なのが発泡スチロールの容器
発泡スチロールはメダカ専用のものができるくらい、メダカの越冬に向いておりその理由は発泡スチロールの性質にあります。
発泡スチロールは急激な温度変化から水温を守ってくれる
気温が急激に変化する冬は水温もその影響を受けやすいですが、発泡スチロールを使うとその変化を緩やかなものにしてくれるうえ、日中の日差しで暖まった水温を保温できるという機能も持ち合わせています。
そのためメダカを越冬させるなら発泡スチロールがおすすめなのです。
メダカ越冬させるためには発泡スチロールをフル活用
メダカを越冬させるなら、発泡スチロールの容器に蓋も準備しましょう。
メダカを屋外飼育している場合、蓋があれば越冬で氷漬けになる心配を最小限にできますし、梅雨や台風などのときの薄い侵入も防ぐことができます。
実は発泡スチロールを水槽代わりにしてメダカを飼育していると、冬だけでなく一年中大活躍することもあるのです。
保温性に優れ、なおかつ適度な密閉性を持つ発泡スチロールは水温管理などもしやすいという利点がある
冬は水温をあたたかく、夏はつめたくという状態を保っていられるのですね。
ではなぜここに蓋が必要か、といいますと先述してもいますが氷漬けになることを防ぐ目的があるからです。
この高い保温性をもっと上げるために、発泡スチロールの板にプチプチシートを巻いたもので蓋を作りましょう。
保温性が高まるので、越冬はらくらくこなせるのではないかと思います。
発泡スチロール以外のものでメダカを越冬させるには
屋外飼育なら発泡スチロール以外にもビニールハウスでの越冬もさせられます。
でも個人の家にビニールハウスを、というのはなかなか大掛かりです。
もし屋外飼育をしていて、水槽がラックの上などにあるならそれをレジャーマットで包むだけでもビニールハウスの中にあるのと同じくらいの効果が得られます。
準備をするものは園芸用の雨よけシートやレジャーマットです。
ラックの上にある水槽をしっかりと覆えるならばっちりです。
メダカを観察しないときは紐などで括り付け、飛ばないように対処だけしておけばOK
発泡スチロールの容器は通販などでも購入できますが、すでに水槽があったり、横からも観察したいという方の場合は、このレジャーマットなどでの越冬が行いやすいかもしれません。
メダカを発泡スチロールで越冬させるときは水深に注意
メダカの越冬での保温についてお話をしてきましたがいくら保温をしたからといって他がおろそかでは完璧に越冬の準備をしたとはいえません。
他の部分もきっちりと準備をしておきたいものです。
保温の次に水深についても準備をしておきましょう。
メダカは寒さに強い生き物です
でも凍ってしまっては為す術がありませんので、水槽内の水すべてが凍るのを防ぐために水深を深くしておく必要があります。
ある程度の推進と水量があれば全体が凍るということはまずないと思いますので、今の水槽のサイズ感が不安だなという場合は大きめのものに取り換えておくことをおすすめします。
メダカは冬の間、低い水温の中でも生きていけるようあまり動きません
動かないことでエネルギー消費量を抑えているのです。
水の表面が凍っていて、中のメダカもじっとしていると少し不安になるかもしれませんが、それはメダカが生きようとしている証拠です。
あまり刺激しないようにしましょう。
冬の間のメダカの餌やり
冬の間、あまり動かないメダカたちはもちろん餌を食べる量も減ります。
日中のあたたかい時間帯に消化不良にならない程度の少量の餌を与える程度にとどめ、様子を見守るという形で飼育をしていってください。
餌の与え過ぎは水質の悪化を招き、その水質の悪化はメダカの越冬失敗、そして水槽全体の全滅へと被害を拡大します。
餌はなくても生きていけるくらいの生き物です。
ほんのわずかな食糧程度で生きていけますので、少ないかなくらいでちょうどいいくらいではないかと思います。
それでも多い場合もありますので、様子を見ながら慎重に餌やりを行って下さい。
メダカの動きを見てエネルギー消費をしているかどうか、が餌の量の判断基準になります。
越冬できる丈夫なメダカですが、気を抜けば全滅を招くこともあるということは覚えておいてくださいね。
メダカの越冬について紹介しました。
メダカの越冬ではほとんど世話を必要としない状態である、ということを大前提にお世話をしていくことをおすすめします。
メダカの生態を良く知り、全滅しない様うまく越冬させてください。





















