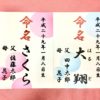礼服に合った靴とはどんなものなのでしょうか?紐のある靴を履くときはこのような靴を選びましょう。靴紐の結び方もシンプルなものにしてください。
葬儀に参列するとき、結婚式に出席するときには礼服に合わせて靴も選ぶ必要があります。
色だけ合わせればいいというものではないので、大人のたしなみとして靴のマナーも取り入れましょう。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

友達への誕生日プレゼント・5000円前後で女友達にプレゼント
女友達の誕生日に、どんな誕生日プレゼントを贈ればいいのか悩んでいる男性もいるのではないでしょうか。...
-

万年筆を保管する時はペン先の向きに注意!万年筆を長く使うコツ
万年筆をずっと長く使い続けるためには、正しい保管が絶対条件。特に万年筆を置く時のペン先の向き...
-

髭の剃り残しをなくす剃り方!T字カミソリで剃る方法とポイント
髭を剃ったとき、うっかり髭を剃り残してしまうことがあります。剃り残しがあると、見た目もよくありません...
-

弁当箱をレンジで加熱したら蓋が開かない!開け方と開かない理由
弁当箱を電子レンジで温めたら、弁当箱の蓋が開かない!という経験をした事がある人もいますよね。せっかく...
スポンサーリンク
礼服のときの靴は紐ありでもいい?葬儀のときの靴のマナー
葬儀に参列する際には「礼服」を着用するのが一般的なマナーとなっていますが、礼服と一緒に履く「靴」にはマナーがあるのか、また、紐がある場合には結び方にもマナーがあるのか気になったことはないでしょうか。
参列前にしっかりと調べておきたいという方も多いと思います。
そこでここでは葬儀に参列する際の靴のマナーについてお伝えします。
よくチェックして「万全」な状態で葬儀に参列できるようにしましょう。
靴の「色」
葬儀参列時の礼服は黒ですから靴の色も礼服に合わせるのが基本です。
ですから靴の色も必然的に「黒」となります。
茶色やベージュ系の色の靴を履くと浮いてしまいますのでくれぐれも注意して下さい。
靴の「素材」
一般的に葬儀では「死」を連想させるようなモノは避けるべきというのがマナーになっていますので、靴の素材でいうのならば「動物の革」を使った素材は避けたおくのが良いです。
ただ革靴の革の種類は豊富です。全てが「合成素材」というわけではなく動物の革を使った俗にいう「本革」の靴もあります。
特に本革の中でも「牛革」を使った革靴は多く着用している人が多いのも事実です。
靴の「デザイン」
デザインは基本的に何も模様等が入っていない「プレーンタイプ」か、模様が入っているとしてもつま先に一本線だけの「ストレートチップタイプ」でなければいけません。
靴の「紐の有無」
紐は前述しました内容が守られていればあってもなくてもどちらでも問題ありません。
ただ紐付きの場合はしっかりと結んでだらしなくならないようにしましょう。
礼服に紐靴を合わせるときは内羽根式
一般的に礼服に紐付きの革靴を合わせる場合は「内羽根式」が望ましいとされています。
ただ靴に関しての知識がそこまで深くない方だと内羽根式ってどんなの?と思うことも少なくないと思います。
内羽根式の革靴の特徴
内羽根式の革靴は甲の辺りの部分の革が内側に収納されているものです。
言葉では説明し難いのですが、革靴を上から見た時に紐の部分の革が上から覆い被さるような形になっていないタイプであれば、内羽根式と判断して良いでしょう。
なぜ内羽根式が礼服にあわせる際に望ましいのか?
内羽根式の革靴は紐を取った場合に羽根がベロンと全開になることがありません。
ただ外羽根式がダメというわけではありませんので、理想は「内羽根式の革靴」ということで覚えておいて下さいね。
礼服の靴として履いてはいけない靴
礼服を着る時に合わせて着用する「革靴」は、光物や素材、デザインに注意しなければいけないということを一番初めにご紹介しましたが、実は学生さんがよく履いている「ローファー」もNGな靴のひとつなのをご存知でしょうか。
その理由はローファーという単語の「由来」にあります。
ローファーは英語で書くと「loafer」です。
靴紐もなくラクに履くことができる靴だからこそこうした単語がつけられたようです。
このようにローファーには怠け者という意味が込められていますから葬儀の場での着用は好ましいとは言えません。
礼服のときの靴紐はこう結びましょう
革靴の一般的な紐の結び方は「シングル」という結び方です。
礼服を着用する際にも基本的にはシングルで問題ありません。
それでは結び方をご紹介します。
革靴の紐の結び方「シングル」
1.はじめに最下段の両穴に靴紐を上から通します。
通し終えた紐が下から出ているか確認後に次に進んで下さい。
2.手順1の右紐を最上段左穴に下から通します。
通した右紐はしばらくこのまま放置です。
3.余っている手順1の左紐は下から2段目の右穴に下から通し、続けて同じ段の左穴に上から通します。
通し終えたら紐が左穴の下から出ているか確認し問題がなければ次に進みます。
4.手順3の段階で2段目まで紐が通っていると思いますので、あとは3段目以降も2段目と同じように紐を通していきます。
最後は最上段右穴に下から紐を通します。
5.あとは最上段の両穴からそれぞれ出ている紐を蝶々結びしたら完了です。
締め付け具合は足を通して調整して下さいね。
シングルはこうやって説明書きをみると一見難しそうに思えますが、実際に紐を通してみると同じ作業の繰り返しでとても簡単に行うことができますので、ぜひ試してみて下さいね。
礼服のときには靴下にも気を配りましょう
今回は礼服着用時の靴や靴紐についてのマナーをご紹介してきましたが、礼服や靴ばかりに気を取られていると「あるところ」で失敗してしまうことがあります。
意外と見落としがちなところ…、それは「靴下」です。
また色と柄以外にも「長さ」にも注意が必要です。
あまり短いものを履いてしまうとズボンの裾が上がった時に肌が見えてしまいますから少し長めのものを選んで履くことも大切です。