メダカの水槽の中に気がついたらヒルがいるけど、どうやって退治したらいいのか悩む人が多いと言います。
一番気になるのはメダカへの影響ですが、ヒルはメダカを食べてしまうのでしょうか?簡単に退治することはできるのでしょうか?
メダカの水槽に現れた「ヒル」がメダカに与える影響と退治方法について説明します。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-
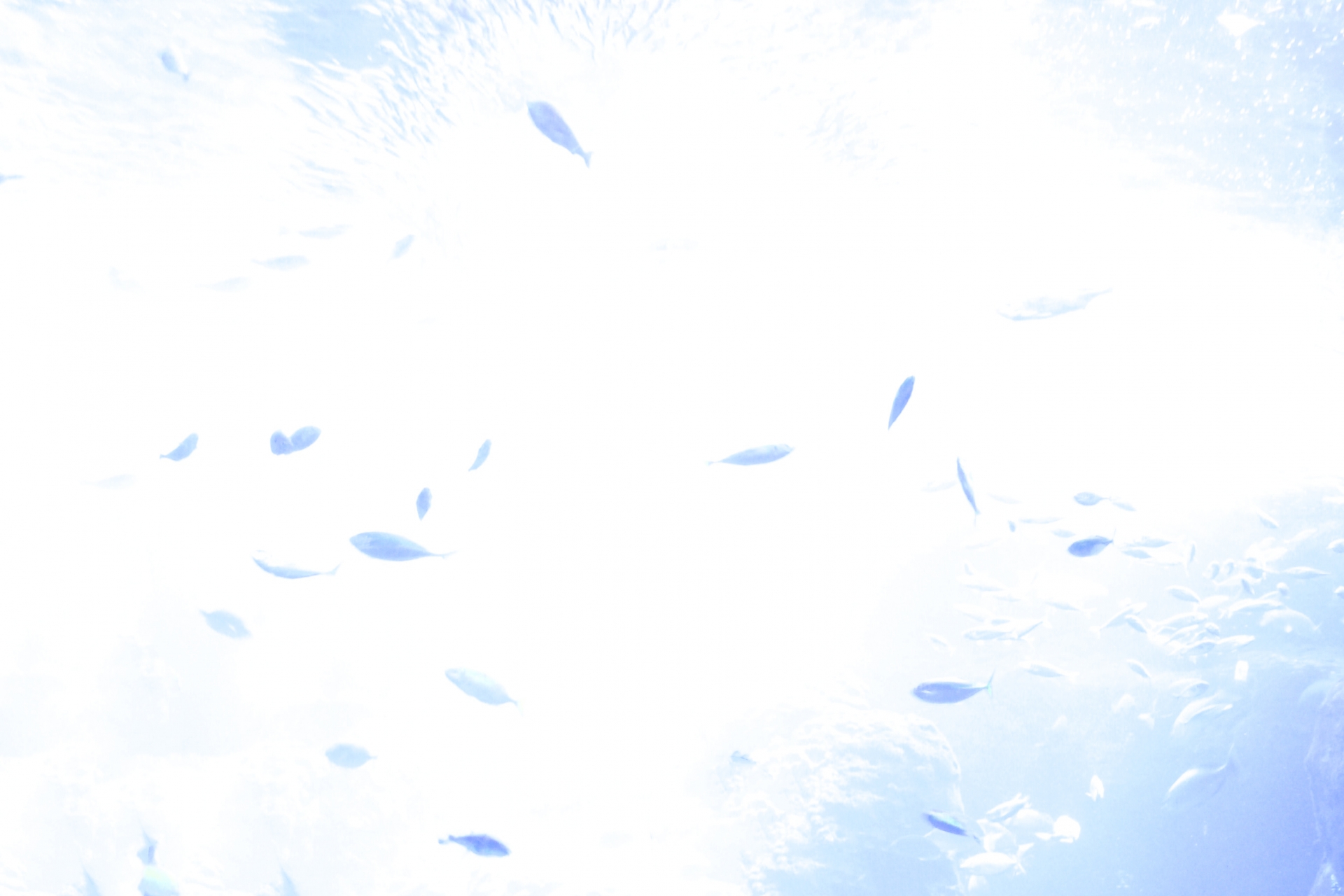
グッピーは出産後もお腹に精子を溜める!グッピーの出産について
グッピーの繁殖に挑戦しているという人もいるのではないでしょうか。まだ繁殖挑戦し始めたばかりだと、出産...
-

カナヘビの卵がへこんでいるのは無精卵の可能性が!卵の見分け方
カナヘビの卵を育てている時、他の卵と様子が違う卵があった場合は無精卵の可能性があります。なかなか卵が...
-

ミナミヌマエビの水槽に入れる水草に付着した残留農薬の除去方法
ミナミヌマエビを飼育している人の中には、水槽の中に水草を入れたいと考えている人もいるのではないでしょ...
スポンサーリンク
メダカの水槽にヒルが…。私はこうやって退治しました
自宅で飼っているかわいいメダカの水槽をよく見たら、中に見たこともない生き物が!なんてことはありませんか?それ、実は「ヒル」かもしれませんよ。
「ヒル」と聞くと、山歩きなどで足にひっついて血を吸われてしまうアレをつい連想してしまいますが、水中に生息するヒルは「イシビル」と呼ばれる別の種類なので、血を吸ったりはしないそうです。実際に孵化したあとのメダカを食べることはありませんが、卵の状態のうちは食べてしまうことがあるので、見つけたら早めに退治しましょう。
水槽内のヒルを退治する方法としては、まだ数が少ないようであれば、1つずつピンセットなどでつまみ出すことも出来ますが、すでに数が多かったり、どこかに隠れているのでは?と不安に思うのであれば、別の方法があります。
まずは、メダカを水とともに別の水槽に移します。そのあとで水槽を熱湯消毒(高温のシャワーでも可)して数分放置するを繰り返し、水で水槽をキレイに洗ったらあとは、日光消毒して完了です。
メダカの水槽にいたヒル「イシビル」はメダカに害があるのかどうか
メダカの水槽の中などにいるイシビルは、体長3センチほどでニョロニョロと蛇のように泳ぐ生物です。普段は水中の微生物や、小さな虫などをエサとしているため、孵化したあとのメダカには直接的な害はありませんので、気にならない方はそのまま放置しても構いませんが、見ていてあまり気持ちの良いものではありませんよね。
キレイな水槽でのびのびと泳ぐメダカたちの姿を楽しむためにも、ヒルを見つけたらなるべく早めに退治してしまいましょう。
ヒルの数が少ない場合はピンセットで退治することも出来ます。水槽から取り出したヒルはすぐに干からびるので、まとめて水と一緒に流してしまいましょう。
しかしながら、ヒルが生息しているということは、さらにその他の害虫も水槽内にいる可能性も高いため、1匹ずつピンセットで除去するよりも、水槽ごと丸洗いして、常にキレイな状態を保つように心がけましょう。
メダカを屋外の水槽で飼育してもヒルは発生します
メダカの水槽を屋外に設置して飼育している場合には、ヒル以外にも様々な生き物を水槽内で目にすることがあります。代表的なものを挙げると、小さな2つの目が特徴的なプラナリアという生物や、白くて糸のように見えるイトミミズ、プランクトンなどです。
これらの生物は、基本的にはメダカと共存させても問題はありませんが、水槽の見た目を重視するならば、やはり定期的に水槽をキレイに洗う習慣をつけ、普段からよく観察するようにしましょう。
自分では水槽内に入れた覚えがないにも関わらず、いつの間にかいることが多い巻き貝などは、水槽に入れるために購入した水草に最初からくっついていた場合が多いです。これらの巻き貝は、メダカのフンや食べ残したエサ、さらに水槽内に発生したコケなどを食べて、水槽内をキレイに保ってくれる役割もしてくれるので、そのままメダカと一緒に共存させるメリットのほうが高いと言えます。
ですが、あまりにも数が増えすぎると水草を食い荒らしたり、水槽の見た目としても気になるようであれば、適当な数に調整する必要も出てきます。
ヒルのような「プラナリア」にも注意しよう
先程少しご紹介した「プラナリア」という生物について、もう少し詳しく見ていきましょう。プラナリアとは、「扁形動物門ウズムシ綱ウズムシ目ウズムシ亜目」という大変ややこしい名前の科目に属する動物の総称です。見た目は少しヒルに似ていますが、小さな2つの目が特徴的で、水槽のガラスにひっついて這い回ったりしています。
主に生物の死骸などをエサとして食べてくれるため、本来はメダカを襲うことはありませんが、数が増えすぎると弱った生物を襲ったり、エサを独占したりすることがあるため、水槽内で大量に発見した際には注意が必要です。
そもそもプラナリアが水槽内に発生する原因としては、購入してきた水草に卵がくっついていたり、メダカを購入してきた時の水に一緒に紛れていたなどが挙げられます。ですから、それらを水槽に移す前の段階で、しっかりと確認することで、その後の大量発生を抑制することが出来ます。
また、それでも大量発生を防げない要因としては、プラナリアが住みやすい生息環境が整ってしまうことです。プラナリアは川の清流域を好む肉食生物であることから、水温が低くてキレイな水とエサが豊富にあるメダカの水槽内は、大量発生してしまう要素が揃っていることになるのです。
メダカの水槽に発生したヒルはヤマトヌマエビで駆除することはできない
メダカの水槽内でヒルを発見したら、直ちに水槽ごと洗い流してしまうのが一番ベストな方法なのですが、繁殖用の稚魚が孵化した直後などは、そう簡単に水質を変えることが出来ませんよね。
ヤマトヌマエビという種類のエビは雑食性なため、お腹さえ空けば何でも食べてしまいます。本当にお腹が空いた時であれば、それこそヒルも食べてくれるかもしれませんが、その反面、よほどお腹が空いていない限りは、水槽に付着したコケすら食べてくれませんので、ヒルだけを退治する目的でメダカの水槽にヤマトヌマエビを入れたところで、期待には答えてくれないと思ったほうが良いでしょう。
仮にお腹が極限まで空いた状態であれば、ヒルどころかメダカの稚魚すらも食べてしまいかねませんので、ヤマトヌマエビに頼ってヒルだけを退治してもらうのは、やはり難しいと言えるでしょう。
























