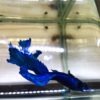犬を撫でようとしたら唸るようになってしまった・・こんなときにはどうしたらいいのでしょうか?
犬を撫でるときに唸るのはどうして?唸るシーンによって犬の気持ちも違ってきます。しつけをするときにはどんなことに気をつけたらいいのでしょうか?
しつけるときにしてはいけない事とは?犬をしつけるときのコツやポイントを紹介します。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

コリドラスの水槽に水草は入れない?おすすめの水草と入れ方解説
コリドラスを飼育するときは、水槽の中に水草を入れずに飼育することが多いです。まだコリドラスの...
-

ウサギのケージの掃除の仕方と道具を紹介。頻度や選ぶポイントも
見ているだけで癒されるウサギはペットとしても人気です。ウサギは自然界では穴で暮らす生き物なので、...
スポンサーリンク
犬を撫でると唸るのはナゼ
優しく撫でたつもりなのに可愛がっている犬から唸り声を上げられたら、飼い主としては少しショックかもしれませんね。
犬と飼い主の関係
犬が唸る原因の一つに、犬が人間よりも偉いと思っている可能性があります。
犬は祖先である狼の習性を受け継いており、厳しい上下関係がある群れで生活します。リーダーを頂点として、立場が下の犬は上位の犬に服従するのです。
また、犬はともに暮らす人間も群れの一員だとみなすため、家族それぞれを順位付けして見ていると言われます。
正しくしつけられた犬の場合
家長をトップとして犬である自分を一番下の立場だと理解します。しかし、自分が人間よりも上の立場だと思っている犬は、人間に対して不満がある時に唸ったり吠えたりといった行動を取ることがあるのです。
撫でた場合や逆に撫でるのをやめた場合、その他にも人間に対して唸る、吠えるなどの行動がある時は順位付けを明確にするようしつけるなどの対策が必要になります。
撫でると唸るときの犬の気持ち
犬が唸るという行動は警戒心を感じている場合が多い
「それ以上近づくな」という警告であると考えられます。
犬自身が恐怖を感じてるのであれば攻撃行動に出ることもあるので、犬から距離を取りましょう。
犬が何かを食べている時や、お気入りのおもちゃで遊んでいる時にも撫でただけなのに唸ることがあります。まだ人間との信頼関係がきちんとできていなかったり、遊んでいて興奮状態にあるときは撫でるタイミングにも注意が必要です。
食事中に人間が手を出しても取り上げることはないと、きちんと教えてあげましょう。
おもちゃで遊ぶ時には、ただ自由に遊ばせるだけでなく「離せ」や「ちょうだい」といったコマンドでおもちゃを離すようにしつけるといいでしょう。
遊んでいるうちに興奮状態になり、唸るようであれば「離せ」と指示して遊びを止めさせて一旦落ち着くように促しましょう。
犬を撫でると唸るのは信頼関係を結べば解決
犬との主従関係
犬を飼う上で重要なのは、飼い主との主従関係や上下関係をしっかりと構築するということです。これができなければ言うことをきかなかったり、無駄吠えや噛み付きなどのトラブルが起こることがあります。
愛犬を大切に思うのであれば、ただ可愛がるだけでなく必要なしつけは厳しく行うべきです。
飼い主に支持されたことには素直に、確実に従うことができれば災害などの緊急時でも安全に避難できる可能性が高まります。近年、自然災害が増えている日本では、災害時のことも備えておく必要があるのです。
犬との信頼関係はコミュニケーションから
ご飯やおもちゃを取られると勘違いして犬が唸ったのであれば、それは信頼関係ができていないのかもしれません。普段からコミュニケーションを密にして、飼い主として信頼されるようにしておきましょう。
まれに取り上げたおもちゃを取り返そうとして勢いよく噛み付き、そのまま誤飲してしまい病院を訪れるケースがあります。愛犬がトラブルを引き起こさないためにも信頼関係は重要です。
犬を撫でて唸るときにはじっくりしつけることが大切
飼育されている犬が唸るケースには、いくつかのパターンがあります。
「所有性」を主張して唸る
動物は「自分の獲物」を取られると怒るのが当たり前でしょう。しかし、飼育している犬が食べてはいけないものを食べようとした場合や、何かをいたずらしようとした時に取り上げることが必要になることもあります。
普段から「離せ」という指示で言うことをきくようしつけることが重要で、唸る場合は叱ってダメなことだと理解させ、言うことを訊いてすぐに離したらご褒美を与えましょう。
「優位性」を主張して唸る
散歩や食事を与える場面で、人間と犬ではどちらがより優位(偉い)であるかを普段からきちんとしつけておくことです。
特に犬がリーダーであると認められた飼い主が、他の家族や人間に対しても唸らないように繰り返ししつけることです。
食べ物をなどを求めて唸る
食べ物を要求するために唸る行動がある場合には「唸ると食べ物はもらえない」と徹底して教えることが重要です。
どんなに欲しそうにしていても、唸っている間は絶対に与えずに唸ることを止めたら与えることを徹底しましょう。
犬を撫でているときに唸るのを止めさせたいのなら叩いてはダメ
犬は叩いても覚えない
犬が唸ったからといって、しつけのつもりで叩くなどの体罰を加えてはいけません。
犬が唸るのは何か不満など「原因」があるからで、不満を訴えたら叩かれたのでは、よりストレスを抱えて問題行動に繋がる恐れがあります。
しつけを行う場合は短い時間で集中的に行います。犬の集中力は10~15分程度しか持続しないと言われ、それを過ぎて何かを教えても非効率なのです。
教えている最中に落ち着きがなくなるなど集中力が途切れたと感じたら、一旦中断して時間を置いて再び教えましょう。
犬が興味を持って集中してくれないのに無理にしつけても、それは犬にとって「嫌なこと」でしかなく覚えてくれません。
また、犬が唸った時に飼い主がひるんだり怖がったりすると犬は「自分の方が立場が上だ」と思ってしまい、その後も言うことをきかなくなることがあります。
常にリーダーは飼い主であり、犬は下位にあるという状態を維持することが重要です。
愛犬との良好な関係のためにも主従関係をしっかりとしつけることが重要
犬が唸る、吠える、指示をきかないといったトラブルの多くは正しくしつけができていないことにあります。
人間よりも自分の方が偉い存在だと思った犬は、不満があると唸るなどの行動を示すようになります。
最悪の場合、噛み付いたりといった問題行動に発展する可能性もありますので、飼い主は常に犬よりも上の立場であるという状態を維持してください。
しつけが上手くいかない場合には、短期的にでも専門のトレーナーなどに相談すると良いでしょう。長い間悩まされ続けた問題行動が、たった数時間程度のトレーニングで直ったというケースは少なくありません。
その場合も、リーダーはあくまでも普段一緒に過ごす飼い主なのだときちんと教え込んでください。