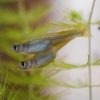オカヤドカリの動く姿を見ていると、なんともかわいらしいですよね。
そんなオカヤドカリは脱皮をしながら成長すると言われていますが、その頻度はどのくらいなのでしょうか?脱皮している時は飼い主として何をしてあげればいいのでしょうか?
オカヤドカリの脱皮の頻度やかかる期間、飼い主がしてはいけないことについて詳しく説明します。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

ハムスターの交配は組み合わせが重要!異種交配は絶対に避けよう
ハムスターの交配では組み合わせによって奇形が生まれてしまったり、病気を引き起こしてしまう事があります...
-

アロワナの水槽の立ち上げ方法・飼育に必要なものと水槽の大きさ
アロワナの飼育を始めようと思っている人は水槽の立ち上げについて知りたいですよね!アロワナを飼育する時...
-

ウーパールーパーのエラをふさふさに戻すには?水質をチェック!
ウーパールーパーには首飾りのようにふさふさしたエラがついていますが、これがふさふさせずに縮んでしまう...
-

グッピーのメスの妊娠はお腹でわかる?見た目でわかる妊娠の兆候
グッピーのメスが妊娠していると、見た目でわかるくらいお腹に変化が見られます。特に出産間近のメスは...
-

ソイルを使った水槽の立ち上げ方法と魚を飼育するまでの管理方法
ソイルを使って水槽の立ち上げをしようと考えている人もいるのではないでしょうか。でも、実際の方法が分か...
スポンサーリンク
オカヤドカリの脱皮の頻度と注意点とは
オカヤドカリは脱皮を繰り返して成長するヤドカリの一種です。
小型の個体なら年に数回、大型の個体で1~2年に1回程度の周期で脱皮を行います。
脱皮は危険を伴う行為
飼育下でのオカヤドカリの死亡原因はそのほとんどが脱皮のときのトラブルによるものなのです。
無事に脱皮を行わせるための管理方法は様々情報があると思いますが、脱皮管理とは基本的に何もしないことなのです。
できることといえばオカヤドカリのために環境を整えてあげることくらいです。
まずは脱皮について考える前に飼育環境が適正かどうかを見ていきましょう。
適正な飼育のためには以下の環境を整えてあげてください。
- 飼育している頭数(60cm水槽なら5匹以下、45cm水槽なら2匹以下というような)を守っている
- 適度に湿らせた砂を15cm以上敷いている
- 飼育容器内部を25℃前後、砂上の湿度70%程度を保っている
- 常に新鮮な真水と海水を利用できるようにしている
- 餌は安全なものをバランス良く与えている
- 飼育容器は静かな場所に置くこと
- ハンドリングは極力避けること
上記の項目が基本的な快適にヤドカリの過ごせる空間づくりのためのポイントです。
まず普段からこうした環境づくりができているかをチェックしていきましょう。
飼い主としてオカヤドカリの脱皮の危険性と頻度について理解しよう
なぜ脱皮をするのか
オカヤドカリに限らずヤドカリの脱皮というものは危険の伴う行為です。
脱皮のときに邪魔が入ってしまうと脱皮不全に陥り最悪の場合、命を落としてしまいます。
そこまでして彼らが脱皮を行うのは成長のためです。
昆虫や甲殻類などの節足動物は成長につれて脱皮を繰り返し大きくなります。
他にも水質の変化でも脱皮をすることが確認されており、水質の比重が急激に変化すると脱皮を行うようです。
ヤドカリが脱皮を行い成長している場合
住んでいる貝殻を引っ越したりすることもあります。
体の大きさに合わせた家を背負って生活するため、脱皮のあとは違うお家を用意しておくとお引越しをしてくれるかもしれません。
また同じ水槽になにか別の生き物を共生させる準備をしたりなどで水質や環境が変化する場合も同じように脱皮の反応を見せることがあります。
もし脱皮を行ったら水質や環境にも気を配ってあげてください。
上記の事からわかるように頻度は数字で表せるものではないのかもしれませんね。
ヤドカリの脱皮の頻度はわかったけど、脱皮前の様子とは
頻度については個体差などもあり大きくばらつきがありますが、前兆というものはあります。
脱皮の前兆として見分けやすいこと
- 眼柄(ヤドカリの目のついている部分の柄)が白っぽくなる
- 餌を普段よりも食べるようになる
- カルシウムの多いものを好んで食べるようになる
- 海水の頻度に浸かる頻度が高くなる
- 動きが鈍くなる
などの前兆行動があるようです。
このような前兆を頼りにもうすぐ脱皮をするのだなと見極めてあげられるとヤドカリも安心して脱皮を迎えられると思います。
そしてもし脱皮がはじまれば飼い主のやるべきことというとそれは一つだけです。
脱皮をしているヤドカリのために『何もせずそっとしておく』というのを心がけてください。
良かれと思ってなにかしてしまったことで、ヤドカリの命を脅かしてしまうこともあります。
ヤドカリのペースに合わせて見守る役に徹しましょう。
オカヤドカリの脱皮に必要な砂の質や量について
ヤドカリは砂に潜って脱皮を行う場合もある
ヤドカリを飼う際には水槽に砂を入れると思いますが、脱皮にも砂を使用する彼らのために水槽の環境をいつでもそのタイミングを迎えられるように準備しておくことも飼い主の努めかと思います。
脱皮に適した環境とは
温度変化が少なく暗く湿っていて他の個体の干渉を受けない状態です。
これらの条件を満たした場所となるとそれは自然に砂の中になっていくのでしょう。
ヤドカリたちは砂の中の巣穴にて脱皮を行うことがほとんどです。
そのため湿り気のある砂を15cm以上は敷いて飼育することを守っていれば環境は悪くないのではないでしょうか。
基本的に砂の中で脱皮を行うヤドカリたちですが、稀に砂の上で脱皮を行うこともあります。
ですがそうした環境で脱皮を行ってしまうと、砂上では体表から充分な水分を吸収することができずそのまま動かなくなってしまう危険などもあります。
また砂上での脱皮は他の個体からの干渉も受けやすく場合によっては共食いなどが起きてしまう可能性もあるので
なるべくならば砂の中で脱皮をしてもらえるように環境をしっかり整えておきましょう。
オカヤドカリの脱皮や体調について
実はオカヤドカリが体調不良でもどんな病気にかかってしまうのかがわかっていません。
そのためオカヤドカリの状態を見て体調の良し悪しを判断する必要があります。
『脱皮不全』にならないために
ヤドカリにとって命がけの脱皮は通常砂の中で行われなるべくストレスの少ない環境を自分で作って行います。
ですが多頭で飼育している場合は鑑賞されて失敗してしまったりということが起きるためできることならば隔離できる環境を作ってあげることが望ましいです。
湿度は高く維持するようにし、脱皮の間は砂を替えることも控えましょう。
ヤドカリが脱皮したあとの殻
カルシウム補給のために脱皮した個体が食べるということが多々あります。そっとしておいてあげましょう。
他にも『貝殻から出てこない』『貝殻から抜け出してしまう』などの行動も体調により行うことがあります。
基本的にヤドカリが貝殻に入ってしまうのは身の危険がある場合ですが、出てこなくなってしまうとそれは体調を崩してしまっているということが十分に考えられます。
原因の特定が難しいため対処が難しいとは思いますが、ケージの砂を洗浄するなど飼育環境の改善を行いましょう。
そして貝殻から抜け出してしまうときも飼育環境に何らかの問題がある場合がほとんどです。
通常貝殻に入って生活するヤドカリは引っ越しのために抜け出ることもありますが、抜け出た状態が何日も続くというのは異常です。
その場合は飼育環境の悪化によりストレスを感じている可能性が高いため、砂や水が汚れていないか、餌が腐っていないかなどを注意しましょう。
ヤドカリと程よく付き合って、ぜひ長生きしてもらいましょう。